戦国時代をこよなく愛する激務ファミレス店長南昌幸がお届けする
ブログにお越しくださいまして、ありがとうございます!
[ad#co-1]
「薬袋」ってこれなんて読むと思いますか?
「くすりぶくろ」?
ですよね!普通はそう読みますよねえ。
でも違うんです。
「やくたい」?
なんか「布袋」(ほてい)みたいですもんね!
でも違います!
ではなんて読むのでしょうか?
答えは、「みない」と読みます!
殆どの方が読めなかったと思います!
どうして、薬袋をみないと読むのか?
この由来について紐解いて行きたいと思います!!
もしご興味がある方は、よろしくお付き合い願えればと思います!
薬袋という地名はある?

山梨県早川町に
まずよくあるのが地名からとったという説が多いようです。
薬袋という地名は果たしてあるのでしょうか?
探しました!
ありました!
山梨県南巨摩郡早川町薬袋!
山梨県の南に位置する山間の町にありました!
やはり、薬袋(みない)と読むようです!
由来はなにか調べてみました!
永田徳本から
すると、1人の医師の名前が出てきました。
その名も「永田徳本」といいます!
安価で治療を行った放浪の医者で、武田信虎、信玄公に仕えていました。
「永田徳本がいれば、薬は要らない=薬袋はみない」というところから、永田徳本先生が滞在した場所の早川町に「薬袋」という地名が付けられたと言われています!
湿布薬などで知られる製薬会社「トクホン」の名前は、この医者の名前にちなんで付けられたそうです!
さらに、もう一つの説も?
和気家から
平安時代、京都で典薬寮という医薬を担当する部署の典薬頭(長官)に和気氏という一族がいました。
その末裔の和気且成がなにかやらかし罪を負い、1289年鎌倉時代に山梨県に島流し?にあいます。
さらに鎌倉時代末期(1331年)、島流しにあった和気且成の孫、和気延成の時代。
鎌倉幕府倒幕運動である元弘の乱の際、和気延成は、京都六波羅探題(幕府の政庁京都支部)攻略において倒幕側(後醍醐天皇、足利高氏)として戦功を挙げ、褒美に皆井(みない)(山梨県早川町役場付近)(早川と春木川が交わる水合(みなあい)の場所でもあります)と呼ばれる土地を賜りました。
そこで、かつて平安時代に祖先が薬を扱う部署を担当していた事から、「薬袋」と書いて、「みない」と呼ぶようになったとか?
またまたもう一つの伝説があります。
厳島姫と池の宮の悲恋
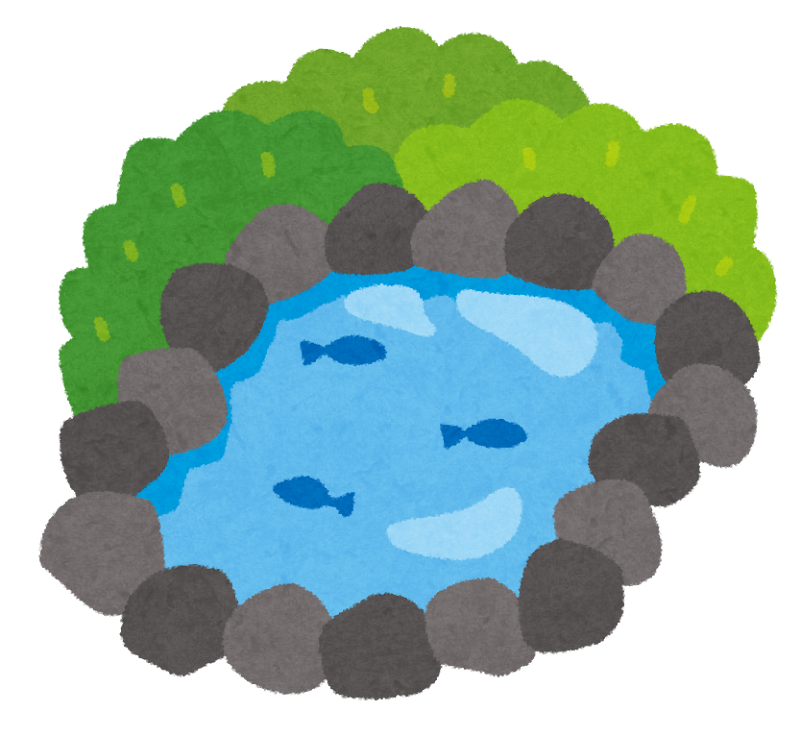
平安時代のころの話です。
京都に住んでいた公卿(中納言藤原家?)の娘(姫)がおりました。
その姫が業病(難病おそらく天然痘)にかかっていて、姫の両親はありとあらゆる治療を試みましたが全く治る気配がありません。
そんな時両親が厳島神社に病気治癒の祈願に出向いたところ、厳島明神からお告げを聞きました。
内容的には「甲斐の国の波木井郷の霊山(後の七面山)に七つの池があり、その水で清めれば治る」というものでした。
実は姫が生まれたのも厳島明神にお祈りした末に授かった娘ということもあり、そのつながりもあったのでしょう。
早速姫は供人を連れて京都からはるばる甲斐の国まで出向きます。

波木井の霊山(七面山)についた一行は笹小屋を作り、姫と老人一人を置いて帰ります。
ある時姫は一人で七面山の一の池というところに行き、その水で清めるとたちまち病気は治りました。
その後姫の体が光り輝き、そして姫は「私はこの池に住まなければならない」、と言って突然池に飛び込みます。
するとなんと姫は龍神に姿を変え、さらにさらに七面天女になってしまったのです!!
その間いつになっても戻らない姫を心配した老人は姫を探すのですが、当然見つけることができずにいました。

一方、当時京都にて姫を想い何度か直接姫に結婚を申し込んでいたけどそのたびに断られていた高貴な若者「池の宮」がおりました。
そんな彼は姫が甲斐の国へ病を治しに旅立ったと聞き、中国で入手した霊薬を持って姫を追いかけます。
その後若者「池の宮」が甲斐の国、波木井の霊山(七面山)に到着すると、とにかく姫を求めて山麓や山の中をくまなく探します。
がすでに姫が天女になった後だったのか探せど探せど見つかりません。
笛を吹いたり経を読んだり琵琶を奏でたりして姫をしのびますが姫は出てきません。
探し疲れた頃でしょうか、姫の付き添いできていて池の宮同様姫を探していた老人と出会います。
そして老人からもやはり姫を見つけられないでいるという話を聞きます。
ただし、この時もしかしたら老人は姫が天女になってしまったことを知っていたのかもしれません。
そしてその話を池の宮にしたとしたら・・・。
最終的には池の宮は姫を探すことをあきらめ(天女になっていたことを知っていたらあきらめざるを得なかった)、持参した薬袋(くすりふくろ)も意味がなくなったと池に捨て、自らも池に身を投げたと伝えられています。

姫が見つからない(ミナイ)で薬袋を捨てた、というところから薬袋(ミナイ)という由来です。
地名についているのはその地を池の宮が歩いた(探した)場所だということです。
しかし、名字としては薬袋という家が現在一件も早川町にはいません!謎です??
その謎は後程!
レア名字BEST3位に輝いた!?

以前テレビ番組で、レア名字のランキングをやっておりまして、そこでまさに3位にランキングされたのがこの「薬袋」という名字でした!
では、そこで紹介されていた名前の由来をご紹介致しましょう!
甲斐の国(現在の山梨県)を治めていたのが武田信玄公でした。
武田信玄公についてこちらの記事を参考になさってください
甲斐の国、戦国大名、武田信玄公は「こじか」タイプ?その中身は?職場にいる?
武田信玄公は、病に侵されていて、薬を手放せない状態でした。
しかし、その病を周りに知らせるわけには行きませんでした!
なぜなら、病気という弱みにつけ込み攻め込まれたり、部下から謀反をおこされる恐れがあったからです。
その武田信玄公があろうことか狩りの最中に薬籠を落してしまい、
それを拾って届けた百姓に「薬袋くすりふくろ」は見たか?と尋ねたところ「みない!」と答えたのでその百姓に「薬袋=みない」という名字を与えたようです!
なんかトンチのようで面白いですが、そういう話が伝わっています!
名前の由来ってこんな感じで付けられるものなんですね!
[ad#co-2]
実際に武田家の家臣に薬袋さんはいたのか?
薬袋と呼ばれる人は、どのような人だったのか?
戦国時代の「薬袋」さんに、「薬袋小助」さんと呼ばれる人がおります。
実は私自身の、今も記録に残る家系図の初代は「薬袋小助」さんなのです。
※三星院(中央市以前の豊富村にある)調べ。三星院を開いたのは武田二十四将の一人、三枝昌貞(守友)の父親、虎吉です。信憑性高いでしょう。
その家系図には、「武田晴信之臣 薬袋小助」と記されています。
また、武田信玄を筆頭とする、家臣の一覧図があるのですが、(信玄公から、武田24将、、と上から下へ書き記した図)この下の方に、小さく「薬袋小助」と書いて在るのです!
間違いないでしょう!
浅利与一公の子孫の一族という話は?

浅利与一公は弓の名手

浅利与一公という人物は、鎌倉時代の弓の名手で、三与一の一人です!
武田信玄公の祖先(武田信義公)と兄弟になります。
鎌倉幕府初代将軍の源頼朝公の幕下で働いていました。壇ノ浦の戦いなどにも参戦しています!
現在の山梨県中央市浅利地区を本拠としていました。
(伝説として伝わるのが、ある時、浅利与一公がそこからかなり離れた川にいる白鷺を弓矢で狙いました。
その弓で弾いた矢が、見事に白鷺に命中します。
しかし、それは白鷺ではなかったのです、、、、。
白い服を来たお婆さんだったのです、、、、。悲しいお話です、、、)
浅利与一のお墓は中央市(旧豊富村)にあります!
浅利与一公の奥さんは板額御前
そして、奥さんは3御前の一人、謀反人の女武将、板額御前だったりします!
堂々たる振る舞いを見た浅利与一公は、時の将軍、源頼家公に謀反人である板額御前と結婚したいと申し出ます!
その時、浅利与一公は、「彼女との間に武勇に秀でた男子を儲けて、幕府や朝廷に忠義を尽くさせたい」と言ったそうです!
男らしい!!!
将軍は、笑ってこれを許したといいます!
なんかいい話ですね!
要するに、武芸に秀でた2人が結婚したのですから、その血筋は武芸に秀でたものが生まれるでしょう!とその通りになっていきます
浅利与一公の子孫は武田家の重臣となる

時は流れ、戦国時代、武田信玄公の時代になります。
浅利与一公の子孫は、武田信玄公の重要な家臣、浅利信種公となります!(赤備えの騎馬を120騎もつ侍大将でした!)
この浅利氏に仕えていた4つの家がありました。
そのうちの一つが、「薬袋」家なのです!
突然出てきた浅利家一族薬袋家。
中央市(旧豊富村)にある私の家に伝わる伝承に、「早川町から家を移築した」という言い伝えがあります。
それが本当なら、早川町にいた薬袋小助さんが、浅利家の本拠地に引っ越しをし、そして武田信玄、もしくは浅利家に雇われたのだと推測することが出来ます!
つじつまがあいました!
また、現在早川町に薬袋さんが一人もいないという謎は、このタイミングで皆引っ越ししてしまったのでしょう!
薬袋の人たちはどこへ
赤備えにいた薬袋藤市さんは武田家滅亡後、井伊直政公について彦根に行ったと言われています!
恵林寺にある宝物殿の資料にも数名薬袋という名前の武士?足軽?のお名前が見えますね。
(武田家滅亡後6.7割の武田家家臣たちは徳川家に引き取られていますが、その中にいらっしゃいました)
他にも浅利信種公が亡くなった後、その部隊は嫡男浅利昌種公、そして土屋昌続公に引き継がれます。
その浅利昌種公についていったのが、薬袋ひょうべえ?(もしくはじょうのすけ?)さんという方で、この方は、武田家滅亡後、浅利昌種公とともに東京都の昭島へ移動し、そこで家系をつなげていったようです。(菩提寺は広福寺)
※一説には武田24将で四天王の一人内藤修理亮昌豊の息子が、武田家滅亡時遠州(静岡)に逃れたが見つかり捕縛されますが、そのさらに息子が徳川家に取り立てられて昭島一帯の領地を与えられたといいます。その時に薬袋さんは内藤家の家臣だったようで一緒に昭島に住み着いたという話もあります。(昭島の初代は薬袋じょうのすけさん?)
実際、昭島市の福島ってところには、薬袋って名字が多くいます!
そして広福寺には薬袋総本家というお墓が内藤家の隣に鎮座しています。
これが列記とした証拠ですね!

(廣福寺の門)


(薬袋家の碑) (内藤昌豊公の孫の墓)
薬袋小助さんは
薬袋小助さんはどうなりましたか?
土屋昌続公の弟の土屋昌恒公(片手1000人切りの勇者)や武田勝頼公と共に、最後まで残った40~50人のうちの1人で壮絶な最期を遂げたと思われます!


(片手千人切りの石碑) (こんな崖で壮絶な切り合いが・・・!)
今は徳川家康公が勝頼公を慰霊するために建立した景徳院にて、勝頼公、夫人、嫡男信勝公のお墓の両脇に祀られています。


(こちら景徳院) (勝頼公が最期自刃した場所)


(このどちらかの墓に薬袋小助さんは祀られています)
しかし、その嫡男、薬袋久右衛門さんというのが生き残っており、その子孫は現在は山梨県の中央市大鳥居にて浅利与一公の墓の近くで今もなお健在です!(ただいま19代目)
たくさん人物が出てきましたので一度整理しました!
| 浅利与一公 | 源頼朝公に仕える |
| 板額御前 | 浅利与一公の奥さん。女武将 |
| 武田信玄公 | 甲斐の国の領主。「薬袋」の名付け親。 |
| 浅利信種公 | 浅利与一公の子孫。信玄公に仕える。赤備えの騎馬隊を受け持つ。 |
| 浅利昌種公 | 信種公の嫡男。赤備え半分引き継ぐ。 |
| 土屋昌続公 | 赤備え半分引き継ぐ。後昌種公へ。 |
| 土屋昌恒公 | 昌続公の弟。信玄公の子、勝頼公と共に最後まで戦い戦死。 |
| 井伊直政公 | 武田家滅亡後、赤備えを引き継ぐ。 |
| 薬袋小助 | 武田家家臣。勝頼公とともに戦死。 |
| 薬袋藤市 | 井伊直政公についていった赤備えの一人。 |
| 薬袋久右衛門 | 薬袋小助の息子。山梨に根付く。 |
| 薬袋ひょうべえ(じょうのすけ) | 浅利昌種公(内藤家子孫の説も)とともに東京昭島へ移動。昭島に根付く。 |
まとめ
薬袋という由来は、武田信玄公が薬を落としたことがきっかけでした。
この時、薬を見ないといったことからこの名字が付きます。
また一説には京都の医薬を扱う一族が島流しにあい、地名と職業をあわせて付けたという話も信憑性があります。
その後、薬袋家は浅利家の一族として、各地で活躍しました。
現在、確実なのは、東京都昭島市、山梨県中央市、滋賀の彦根あたりで子孫が引き継がれています!
こういうレアな名字の由来を追ってみるのも面白いですね!
あなたの名字の由来はご存知ですか?

板額会は、浅利与一義成公の妻、板額御前のふるさと新潟県胎内市で活動している市民有志の歴史愛好グループです。
板額御前を話題にしてくださっているのが嬉しくてコメントしました。
浅利さんの一族はかなり栄えたのでしょうね、あちこちに「私はその子孫です」と名乗る方がいらっしゃいます。たまに「与一さんの嫁に会いに来た」といって、わざわざ胎内市まで遊びに来てくださる方もいらっしゃいます。
薬袋さんもご一族なんですね。記事が面白くて一気に読みました。
よしかったら板額会のfacebookや胎内市ホームページも覗いてみてください。
板額会さん、ブログをお読み下さり、またコメントまでくださりありがとうございます!
私は、浅利与一の墓がある、山梨県中央市大鳥居の出身です。(今の住まいは神奈川県ですが、、、)
板額御前の話は、山梨の実家の母親が踊りをやっていまして、その関係?で新潟に行き
仕入れてきた話しを聞いたところから、私も興味を持ち、ブログに書いた次第であります。
今度もう少し詳しい話を母に聞いてみたいと思います。
また、板額会のFacebookと胎内市ホームページも見させていただきたいと思います!
ご紹介ありがとうございました!
先祖が薬袋と申します。某県立図書館古文書館の先祖書に先祖(薬袋弥左衛門尉 定房)武田信玄公に仕官仕り候と書いてあります。徳川親藩の藩でした。江戸時代の初めに移ったようです。家紋は五本骨扇、浅利家と同じでしょうか? 信玄公の薬袋を拾ったとnhk でも言っていましたが、時代に無理があるそうです。 ネットで調べたので正しいかはわかりませんが、1289年甲斐に流された和気家の孫が、元弘の乱で戦功があり皆井村を賜り、典薬頭を務めた家柄なので(薬袋)の字をあてた。とあります。
コメントありがとうございます。薬袋弥左衛門さんというお方がご先祖様なのですね。
私の祖先はブログにも書いたように薬袋小助さんです。
小助さんが記録に残っている限り私の家の初代になります。私の菩提寺の家系図に武田晴信家之臣と書かれていました。
死亡年月は不詳と書かれていますが、、、一説には勝頼公とともに亡くなられたと(1582年)
小助さんの長男が薬袋久右衛門さんで元和3年(1617年)に死亡されています。
元和3年を調べましたところ、徳川家康が亡くなった翌年のようです。
その方も含め数えて私で19代目ということになります。
ところどころ養子をもらっているので、血は小助さんを純粋には受け継いではいないようですが。
ところで薬袋の由来ですが、この件に関しましては、はっきりとした独自の資料を持ち合わせておりません。
私もネットで調べたところ、和気氏が由来という記事にたどりつきました。
弥左衛門さんがおっしゃるように皆井村というは今の早川町のことのようで、実際和気氏家系図に薬袋という名前が残っているようです。
さらに前出の私の祖先薬袋小助さんも薬袋(皆井)小助って書かれている記事も多くあり、早川町と関わりがあったのかもしれません。
そもそも私の実家は早川町から移築したっていう説も伝わっており、そうなると小助さんが早川町から引っ越しされてきたのでは?とも考えられます。
となると、和気氏由来が本当かもしれませんね。
武田信玄、もしくは浅利家に仕えるために引っ越しされたのでしょう。
家紋なのですが、私の家の家紋は未確認です。
わかりましたらまたコメントしたいと思います!
ドンドン記事が充実して来てすごいです。薬袋小助さんは最も有名な薬袋さんですね。最後まで主君を守り討ち死にしたと聞いていたので、子孫がいるとはびっくりです。天正壬午起請文に、武田滅亡後徳川家に従った薬袋家が何人か載っています。私のご先祖の弥左衛門とその息子金蔵の名はありませんでした。亡き父曰く系図の頭には源氏のお姫様の子守役だったと書いてあった、そうですが空襲で焼けて確かめ得ません。五月の山梨の風林火山の旗を見ると何故かドキドキします。又行きたいです。
弥左衛門さん、コメントありがとうございます!
小助さんの家系図によると、途中、男子が生まれず、婿をもらっている箇所が3回程ありますので、かろうじて血はつながっているって感じです。
弥左衛門さんのご子孫が、源氏のお姫様の子守役とはすごいですね!空襲で焼けてしまったのは残念。
私、今年は初詣に武田神社に行きました。
信玄公祭りはいつも仕事が忙しくて行けていませんが、今度、小助さんのお墓参りにでも行きたいものです。